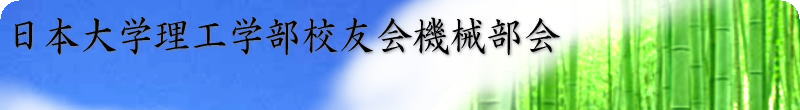 |
| ■沿革 |
理工学部校友会(工科校友会)は,大正13年5月25日に発足した高等高学校校友会がその母体と言われている。発足の経緯は興味深く,前日の5月24日に行われた第2回高等高学校の卒業式(土木21名,建築45名,機械41名)後の謝恩会の席上で来賓の第1回卒業生からその結成が強く提議され,翌日には発足式が挙行されると言う,母校愛の発露とも言える発足であった。 一方,全日本大学としての性格を持つ校友会は,明治26年に発足した日本法律学校校友会がその始まりである。日本法律学校は明治36年に大学組織となり,大正9年に大学として認可されて今日の日本大学の発展を築いたが,昭和15年には校友が約7万人となったことを機に,日本大学本部内に「日本大学校友会」が組織された。日本大学校友会は戦後しばらくの活動を停止していたが,昭和23年3月,戦後停止状態にあった日本大学校友会が新発足し,これに合わせて工科校友会を含む各学部の校友会も,部会として参加することになった。 機械工学科は,1921年(大正10年)に「機械科」として設置された。その後,1929年(昭和4年)には工学部設置に伴い,専門部工科機械学科が設立されている。1949年(昭和24年)には,工学部(現 理工学部)発足に伴い,「機械工学科」としての現在の原形が形成されるに至った。また,1953年(昭和28年)には,工学研究科博士課程機械工学専攻が設置され,名称変更などを伴いながら,現在に至り,卒業生は延べ22,000人にのぼる。校友会機械部会は,これらの卒業生によって構成され,卒業生同士の交流をはぐくみ,在学生への支援などを行っている。 |
| 年 表 | ||||
| 年 | 月 | 理工学部 | 機械工学科 | 校友会 |
| 1889年 明治22年 |
10月 | 山田顕義らにより日本法律学校が設立。 | ||
| 1903年 明治36年 |
8月 | 校則を改め大学組織となり日本大学と改称。 | ||
| 1920年 大正9年 |
4月 | 大学令により大学設立認可。 | ||
| 同 | 6月 | 日本大学高等工学校(土木,建築)設置(理工学部の基盤となる)。 | ||
| 1921年 大正10年 |
4月 | 高等工学校に機械科設置。 | 高等工学校に機械科設置(9月25日開講)。 | |
| 1924年 大正13年 |
5月 | 駿河台校舎で高等工学校校友会の創立発会式。 | ||
| 1928年 昭和3年 |
4月 | 日本大学工学部(土木,建築,機械,電気の各学科)設置(現在の理工学部に発展)。 | 工学部に機械科設置。 | |
| 同 | 7月 | 工学部1号館竣工。 | ||
| 1929年 昭和4年 |
4月 | 日本大学専門部工科設置(土木,建築,機械,電気の各科)。 | 専門部工科に機械科設置。 | |
| 1938年 昭和13年 |
3月 | 工学部,専門部工科,高等高学校に工業化学科設置。 | ||
| 同 | 7月 | 工学研究所設置(理工学研究所の前身)。 | ||
| 1947年 昭和22年 |
4月 | 専門部工科を第二工学部として福島県郡山市に移転(現工学部)。 | ||
| 1948年 昭和23年 |
校友会工学部会(工科校友会)発足。 | |||
| 1949年 昭和24年 |
2月 | 学部改正により,新制大学に改編設置移行。工学部第一部(昼間部)(土木,建築,機械,電気,工業化学)設置。 | 工学部第一部に機械工学科設置。 | |
| 同 | 3月 | 工学部第二部(夜間部)(土木,建築,機械,電気,工業化学)設置。 | 工学部第二部に機械工学科設置。 | |
| 1950年 昭和25年 |
3月 | 短期大学(工業技術科,応用化学科,建設科)設置。 | ||
| 1951年 昭和26年 |
4月 | 新学制による大学院工学研究科(建設工学,機械工学,電気工学,応用化学)設置。 | 大学院工学研究科に機械工学専攻を設置。 | |
| 1952年 昭和27年 |
2月 | 工学部に薬学科設置。工業経営学科(生産工学部の基礎となる)設置。 | ||
| 同 | 10月 | 日本大学短期大学を日本大学短期大学部と名称変更。 | ||
| 1953年 昭和28年 |
3月 | 大学院工学研究科博士課程(建設工学,機械工学,電気工学,有機応用化学)設置。 | 大学院工学研究科博士課程に機械工学専攻を設置。 | |
| 同 | 10月 | 現駿河台校舎5号館の所在地に日本大学工学研究所試作工場(木造工場)を開設。 | 日本大学工学研究所試作工場(現工作技術センター)の開設。 | |
| 1955年 昭和30年 |
桜工創刊。 | |||
| 1956年 昭和31年 |
工学部機械工学科に航空専修コース(航空宇宙工学科の前身)を設置。 | |||
| 1958年 昭和33年 |
1月 | 日本大学工学部に物理学科を設置し,理工学部と名称変更。 | 会則を改正:会長任期を2年とする。 | |
| 同 | 9月 | 江東区大島町に試作工場ならびに内燃機関実験室,駿河台1号館地下に試作工場分室を開設。 | ||
| 1959年 昭和34年 |
1月 | 理工学部に数学科設置。 | ||
| 1961年 昭和36年 |
7月 | 理工学部に交通工学科,精密機械工学科を設置。 | ||
| 1963年 昭和38年 |
3月 | 大学院工学研究科修士課程,博士課程に,物理学,数学,地理学専攻を増設して,理工学研究科と名称変更。 | ||
| 同 | 4月 | 理工学部理工学研究所設置。 | ||
| 同 | 12月 | 日本大学原子力研究所設置。 | ||
| 1965年 昭和40年 |
3月 | 習志野校舎1・2・3号館竣工 | 習志野校舎新設に伴い,3号館地下に中央実験室を開設。 | |
| 1971年頃 昭和46年頃 |
精密機械部会発足。 | |||
| 1972年 昭和47年 |
4月 | 理工学部建築学科(海洋建築コース),機械工学科(航空宇宙コース),電気工学科(電子コース)の3コース設置。 | 機械工学科の航空専修コースを航空宇宙コースに名称変更して設置。 | |
| 1973年 昭和48年 |
3月 | 大学院理工学研究科修士課程・博士課程建設工学専攻を土木工学専攻と建築学専攻に分離。 大学院理工学研究科修士課程応用化学専攻と博士課程有機応用化学専攻を修士・博士課程工業化学専攻と変更。 |
||
| 1977年 昭和52年 |
12月 | 理工学部第一部に海洋建築工学科,航空宇宙工学科,電子工学科を設置,翌年4月から習志野校舎で授業開始。 | 機械工学科航空宇宙コースは航空宇宙工学科へ移設。 | |
| 1979年 昭和54年 |
3月 | 大学院理工学研究科博士前期・後期課程に交通土木工学・海洋建築工学・精密機械工学・航空宇宙工学・電子工学の各専攻設置。 | ||
| 同 | 9月 | 理工学部交通工学科を交通土木工学科と名称変更。 | ||
| 1983年 昭和58年 |
5月 | 飛翔会(航空宇宙部会)発足。 | ||
| 同 | 9月 | 理工学部第二部を廃止。 | ||
| 1984年 昭和59年 |
12月 | 習志野校舎に日本大学理工学研究所機械実習所を開設(大島実験所の全設備を移転)。 | 習志野校舎に日本大学理工学研究所機械実習所を開設。 | |
| 1987年 昭和62年 |
12月 | 理工学部薬学科が分離独立し日本大学薬学部設置。 | ||
| 1992年 平成4年 |
4月 | 大学院理工学研究科博士前期課程に不動産科学,医療・福祉工学,情報科学,量子理工学の各専攻を設置。 | ||
| 同 | 7月 | 新潟県六日町に「日本大学八海山セミナーハウス」開設。 | ||
| 1994年 平成6年 |
4月 | 大学院理工学研究科博士前期課程不動産科学,医療・福祉工学,情報科学,量子理工学の各専攻に博士後期課程を設置。 | ||
| 1996年 平成8年 |
4月 | 東葉高速線「船橋日大前」駅開設。習志野校舎を船橋校舎と名称変更。 | ||
| 同 | 4月 | 機械実習所を工作技術センターと名称変更。 | 機械実習所を工作技術センターと名称変更。 | |
| 1999年 平成11年 |
4月 | 理工学部工業化学科を物質応用化学科と名称変更。 | ||
| 2001年 平成13年 |
4月 | 理工学部交通土木工学科を社会交通工学科,電子工学科を電子情報工学科,大学院理工学研究科博士前期・後期課程交通土木工学専攻を社会交通工学専攻と名称変更。 | ||
| 2002年 平成14年 |
3月 | 日本大学原子力研究所を日本大学量子科学研究所と名称変更。 | ||
| 同 | 6月 | 「工科校友会」より「理工学部校友会」に名称変更。 | ||
| 2003年 平成15年 |
3月 | 駿河台校舎新1号館竣工。 | ||
| 同 | 4月 | 大学院理工学研究科博士前期・後期課程工業化学専攻を物質応用化学専攻と名称変更。 | ||
| 2004年 平成16年 |
3月 | 船橋校舎14号館竣工。 | ||
| 同 | 4月 | 日本大学理工学部科学技術史料センター(CST MUSEUM)設立。 | ||
このサイトについて |